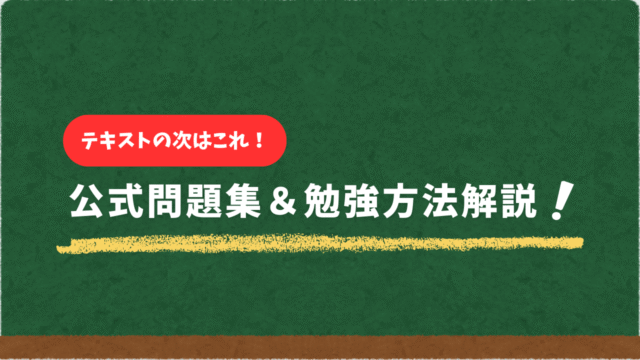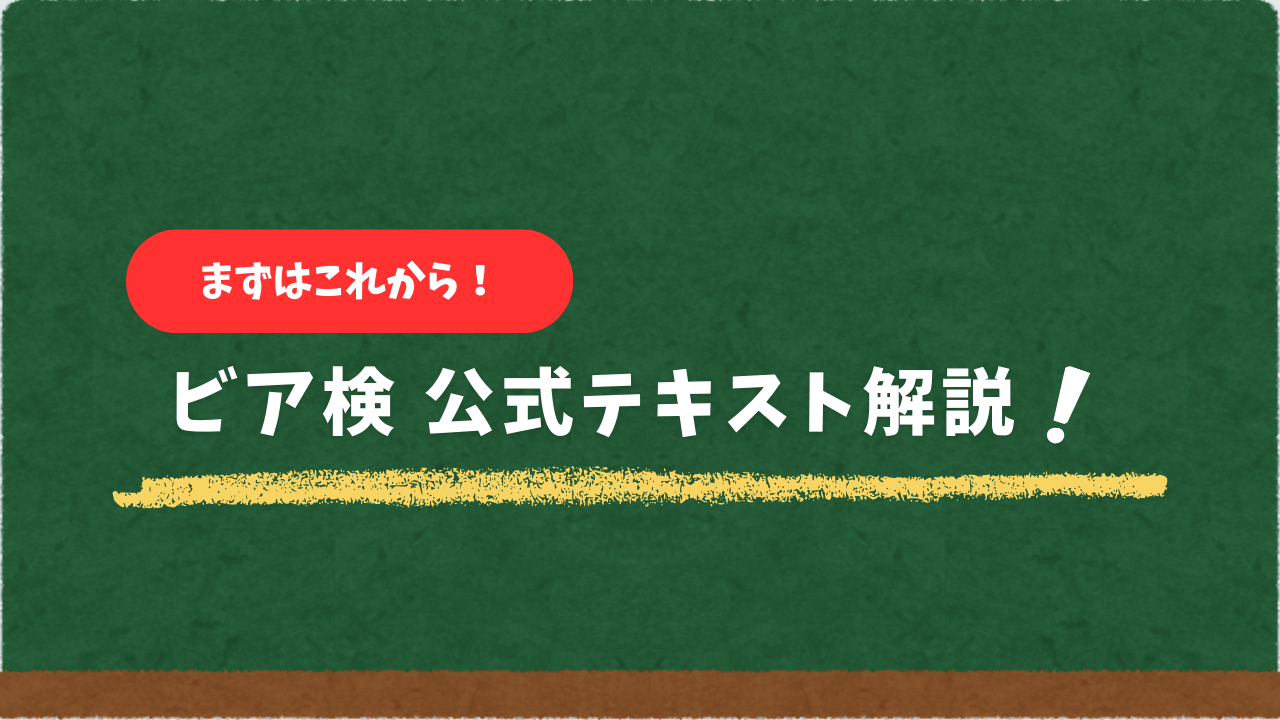「ビア検はどんな知識が試されるの?」「どんな問題が出る?」
この記事では、ビア検の出題範囲、どんな知識が試されるかを解説したいと思います。
問題は、5つのジャンルに分かれる
ビア検は公式の過去問題集があります。この問題集では
1.基本、原料
2、製法、スタイル
3、歴史
4、文化、飲み方
5、雑学
の5つのジャンルに分類されています。
それぞれのジャンルをについて、一つずつ詳しく見ていきましょう。
1.基本・原料
まずは、ビールの基本・原料。
ここでは、ビールの分類や定義、酒税法関連の問題が出題されます。
「ビールは法律上どのように定義されるか」「ビールと発泡酒との違い」「酒税率の違い」
といった問題が出題されています。法律上の定義がなかなか細かいので、しっかり覚える必要があります!
ビールの構成要因となる麦芽・ホップ・水・副原料・酵母についての問題もこの範囲です。
「大麦の構造」「ホップの種類」「主な副原料」
といった問題が出題されています。生物・化学の知識があると有利です!
2.製法・スタイル
次に、製法とスタイル。
製麦・仕込・発酵・貯蔵・ろ過・パッケージング…と、ビールの製造過程が問われます。
醸造についての知識がないと「なんのこと??」ってなりますよね。。
テキストでの学習だけでなく、工場見学やブルワリー見学など、実際の製造過程を見ると、理解の促進に繋がると思います。
ビールのスタイル(種類)もこの項目です。世界各国のビールや銘柄について出題されます。
ここに関しては、暗記しなければならない項目もありますが…知識を入れながら実際に飲んで学ぶべし!だと思います。
文字を追いかけるだけではなく、香りや味と一緒に覚えるのが吉です。
3.歴史
続いては歴史について。古代から現代にかけて、世界と日本のビール史が問われます。
歴史なので、がっつり暗記科目です。世界史・日本史に強いと若干有利かな?
余裕があれば、テキストだけでなくビールに関する書籍を読むと、より理解が深まると思います。
4.文化・飲み方
続いては、文化と飲み方について。
ビールを飲める施設やイベント、ビール文化を支える団体、ビールの味わい方、楽しみ方、アルコールと健康の関係についてなど…多岐にわたって問題が出題されます。
アルコールと健康の関係については、毎年確実に出題されている印象です。健康にビールを楽しんでほしい…という出題者の意図が感じられます。
1級を受験するなら、各団体が開催する品評会・受賞銘柄の暗記はマストです!!
5.雑学
最後は雑学。ここが一番幅広い!
大手メーカーの新商品、CM、クラフトビールについてのトピック、各種機関の調査結果、お酒に関するワードトピックなど…とにかくなんでも出てきます笑
とにかくビールに関する情報への感度を高めましょう!ある意味、一番ビール愛が試される設問かもしれません。
まとめ
以上、5つのジャンルについて簡単に解説しました。
出題比率はおおむね一定になるようです。実際の試験では、ジャンル別ではなくランダムに出題されます。
公式テキストも読みながら、ぜひ学習を進めてみて下さい。
それでは、また!